
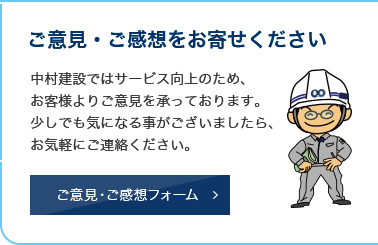
こんにちは! 奈良県を拠点に、大阪・京都・神戸など関西一円で建設業をおこなう中村建設(株)のサチです。
いろいろなしきたりが残っていたり、節目ごとの行事を大切にする建設業界。弊社も朔月参りをした記事をちょこちょこ投稿しておりますが、「安全」に工事を進めていくには、人間の努力だけでなく、自然の持つ大きな力に委ねるところがあるのを知っているからですね。

例えば、昔はトンネル工事に女性を入れてはいけないと言われていたこともありました。山の神様は女性なので、嫉妬して山が崩れるからという言われがあるそうです。
建設業界で、昔ながらの行事として、有名なところでは、地鎮祭、上棟式(棟上げ式)などでしょうか。地鎮祭は、その土地の神様に工事をする挨拶と、無事に工事が進められるように祈願します。上棟式は、工事の途中で基礎の骨組みができたところで、ここまでの工事の無事完了へのお礼とこれからの無事を祈願します。携わってくれた大工さんや施工会社、工事に関わってくれた人に感謝するという意味もあります。
上棟式では、地域によって近所の人を集めて、屋根の上からお菓子を配る風習が残っている場所もあります。近所の人への挨拶を兼ねていたんですね。
建設業界には、中国から伝わった北斗七星を基準に吉方を決める「建築吉日」があります。「建築吉日」は「十二直」という暦の中の一つです。現在の吉凶を占う「大安」「末吉」などは「六曜」という暦から来ています。
ちなみに、月火水木金土日は、「七曜」という暦です。
「十二直」と呼ばれるその暦は、古代中国の暦に由来し、暦注(こよみの吉凶を示す情報)の一つです。これは十二支と同じく12種類あり、日ごとの吉凶が北斗七星の動きを基にして作られたもので、農作業や建築、結婚式などの行事における吉凶をする判断に使われてきました。
干支と同じように12節に分かれていましたが、現代では、たつ(建)、みつ(満)、たいら(平)、さだん(定)、なる(成)、ひらく(開)の6つが建設業界では使われ、地鎮祭や上棟式の日取りを決める際の参考にされています。
この「十二直」とよばれる暦は、奈良県飛鳥村の石神遺跡で出土した木簡にも書かれており、そこで発見されたものが、日本で最古の暦と言われています。明治よりも以前には日本で普及していました。ただ、少し複雑で、毎年固定ではないので、今のカレンダーには七曜が使われています。
自然の力を大切にする建設業界では、古くから伝わる伝統がまだまだ、息づいています。
